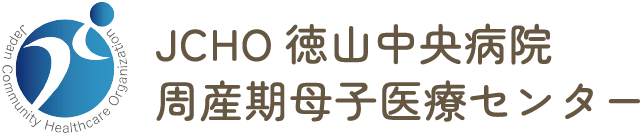
助産師外来
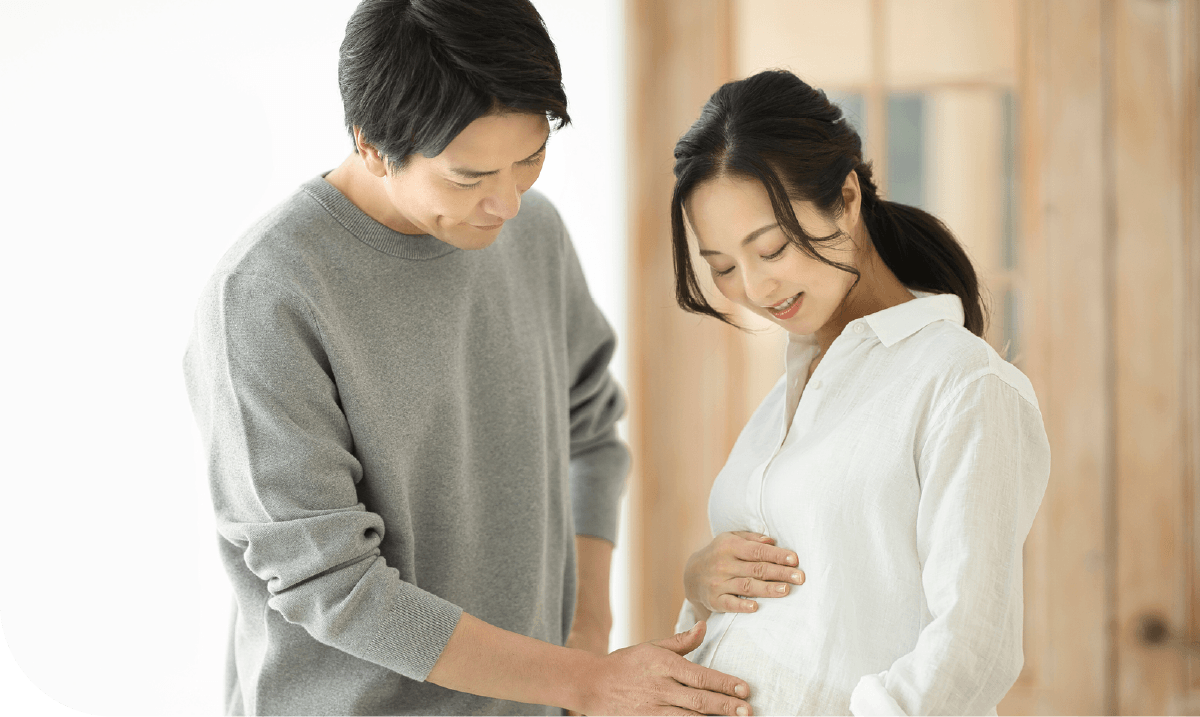
あなたと赤ちゃんのための
安心サポート

妊娠中は、さまざまな不安や疑問が頭をよぎることも多いかと思います。そんなときに心強い味方となるのが「助産師外来」です。助産師は、出産と育児のプロフェッショナルとして、あなたの体調や赤ちゃんの様子をじっくり確認しながら、日々の悩みや疑問に寄り添います。食事や体重管理、運動のアドバイスから、出産に向けた心の準備、育児の相談まで、さまざまな話題をリラックスした雰囲気で相談できるのが助産師外来の特徴です。
妊娠中は心も体も変化の連続です。「こんなこと相談してもいいのかな?」と思うことでも、助産師には安心してお話しください。
助産師外来のメリット
01ゆったりとした時間でのケア
01ゆったりとした時間でのケア
助産師外来では、通常、医師の外来よりも時間をかけて妊婦さんと向き合います。質問や不安にじっくりと応じ、妊娠中の変化や体調について丁寧に確認します。妊婦さんの気持ちに寄り添い、個別にサポートすることができます。
02妊娠・出産への不安や悩みに
対するきめ細かいサポート
02妊娠・出産への不安や悩みに
対するきめ細かいサポート
助産師は、妊娠や出産に関する経験が豊富で、身体的なケアだけでなく、精神的なサポートも得意としています。特に、初めての妊娠で不安がある方や、過去に難しい経験をした方にとって、心強い存在です。
03出産に向けた準備やセルフケアのアドバイス
03出産に向けた準備やセルフケアのアドバイス
助産師は、出産に向けた心と体の準備をサポートします。妊娠中に必要な運動やストレッチ、リラックス法、食事に関するアドバイスなど、妊婦さんが自宅で実践できるセルフケアについても具体的に教えます。
04母乳育児に関するアドバイス
04母乳育児に関するアドバイス
母乳育児に関する質問や不安にも対応し、授乳方法や乳房ケアについてのアドバイスを提供します。産後に備えて、母乳育児の準備をしっかりと進めることができます。
05妊娠経過の自然な観察
05妊娠経過の自然な観察
助産師は、正常で自然な妊娠経過をサポートする専門家です。低リスクの妊婦さんに対して、過度な医療介入を避け、自然な妊娠・出産を目指すためのケアを行います。妊婦さんが自身の身体の変化を理解し、自然なプロセスを受け入れることを促します。
06出産のイメージトレーニングやお産の準備
06出産のイメージトレーニングやお産の準備
助産師外来では、妊婦さんが安心して出産に臨めるよう、具体的なイメージトレーニングを行ったり、陣痛やお産に向けた準備をサポートします。出産の流れや痛みへの対処法、リラックス法を学ぶことで、妊婦さんの不安を軽減いたます。
07信頼関係の構築
07信頼関係の構築
助産師と妊婦さんとの間で、親密な信頼関係を築けることも大きなメリットです。妊娠中から顔なじみの助産師にサポートしてもらえることで、出産当日も安心感があり、スムーズなコミュニケーションが取れます。
08出産後のサポートも継続
08出産後のサポートも継続
助産師外来では、出産後の育児や授乳、体調管理についても継続的にサポートを受けることができます。母親となったばかりの時期に心強い存在として、出産後も寄り添い続けてくれる点が大きな利点です。
09医師の診察との連携
09医師の診察との連携
助産師外来は、必要に応じて医師の診察とも連携し、万が一リスクが高まった場合には迅速に医療介入が行われます。これにより、安心してケアを受けることができます。
Q & A

助産師外来では
何をするのですか?
妊婦健診で行う計測、超音波検査、胎児心音検査、保健指導、相談などを助産師が行います。もちろん、産後のフォローアップもしていますので、授乳に関するお悩みもお気軽にご相談できます(母乳外来)。
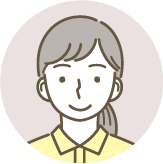
ゆっくり話を
聞いてほしいな
完全予約制で約60分程度時間をかけてサポートいたします。一人ひとり、心配な事を聞いたり、赤ちゃんのことをゆっくりお話したりすることができます。

どんな人が
受けられますか?
妊婦さん自身の希望があること、医師の許可があること、異常がないことなどの基準があります。里帰りの方、途中からの希望の方も歓迎です。希望される方は、医師・助産師にご相談下さい。
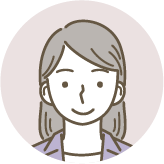
先生の診察を受けなくても
大丈夫ですか?
健診内容は常に医師と共有しています。28週頃・32週頃・36週頃・39週は医師の診察を受けていただきます。急に異常が見つかった場合や、やっぱり先生がいいな…と思われた時は医師外来への変更も行えます。

上の子や夫も一緒に
行っていいですか?
完全予約制なので、家族の方も一緒に、超音波で赤ちゃんを見たり心音を聞いたりできます。お父さんやお兄ちゃんお姉ちゃんになる準備を、ご家族と一緒に考えるのもいいですね!
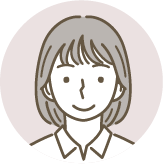
予約はどうするの?
待ち時間は?
健診終了時に、次の予約を「助産師外来」とお伝え下さい。完全予約制ですので、待ち時間がほとんどありません。

料金は別途
かかりますか?
妊婦健康診査補助券を使用することができますので、ほとんどの方は負担がありません。県外からの里帰りの場合は、自治体によっては補助券が使用できないことや、あとから清算されることもありますので、あらかじめ各自治体にご相談ください。自己負担の場合は、医師外来と同じ料金になります。